目次
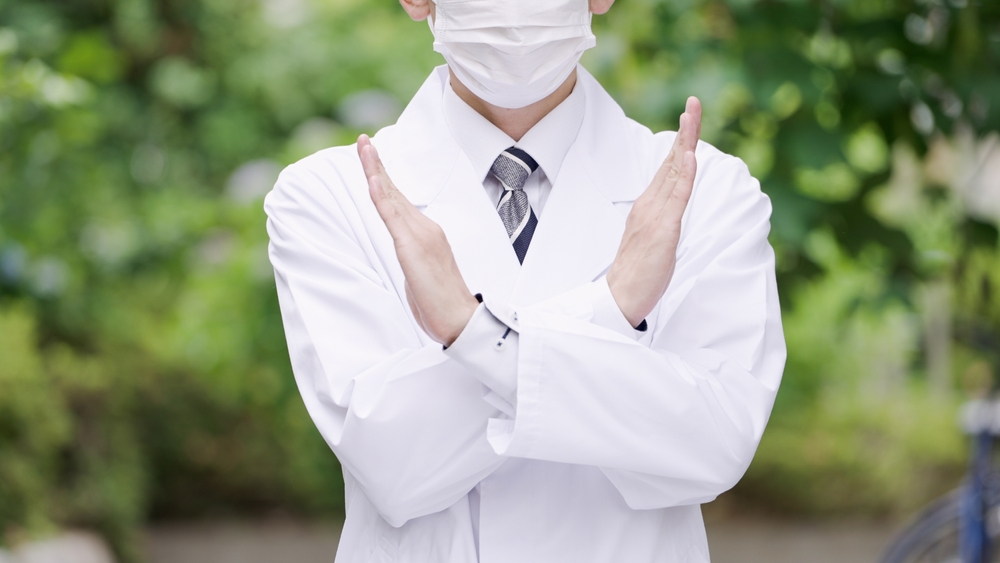
医療DXは、診療・事務・経営の質を引き上げるためにデジタル技術を取り入れ、現場のやり方そのものを見直す取り組みです。
しかし多くの医療機関では、IT環境の未整備、既存システムの分断、教育や人材の不足、投資判断の難しさ、そして変化に対する不安が重なり、思うように前進していません。紙や口頭での引き継ぎ、部門ごとに異なるツール運用、データの重複入力といった日常のつまずきが積み重なるほど、医療DXは「進めたいのに進まない」状態に陥ります。
ここでは、停滞を生む背景を構造的に捉え、現場で何が起きているのかを具体的に解説します。
医療DXは、電子カルテやオンライン診療、AIの診断補助、予約・会計のデジタル化、データ連携基盤の活用などを通じて、患者体験の向上と業務効率の両立を目指す継続的な改善プロセスです。
理想は、受付から会計、地域連携まで一貫してデータが流れる状態ですが、現場では部門単位の最適化にとどまり、院内外の情報が分断されがちです。さらに、導入後の運用設計や人材育成が後手に回ると、システムが活かされず「使いづらい」という印象だけが残ります。
結果として、重要性を認識していても最初の一歩が踏み出せない、あるいは試行導入で止まるといった停滞が続いています。
ITに不慣れなスタッフが一定数いると、デジタル化の意義は共有できても日常運用でつまずきが起きやすくなります。基本操作の不安、セキュリティ理解のばらつき、設定変更への心理的負担は、せっかく導入した仕組みの活用度を下げ、結果的に「DXは業務を複雑にする」という誤った印象を広げます。
教育の機会が不足している組織ほど、属人的なやり方に戻りやすく、改善の勢いが途切れてしまいます。
同じ部署でも、ショートカットや基本設定に慣れた人と、文字入力やファイル保存に時間がかかる人が混在するのが実情です。
ベテラン職員ほど紙の記録や既存フローに安心感を持ち、電子カルテやポータルの画面遷移が増えるほど心理的な負担が大きくなります。結果として、入力スピードの差が待ち時間や残業時間に波及し、「DXは忙しさを増やす」という印象を生みます。
本来はテンプレート化や音声入力などで負担を減らせますが、最初の設定や練習の段取りがないと定着せず、紙とデジタルが併存して二重管理になることも少なくありません。こうしたギャップはヒューマンエラーの原因にもつながります。
導入研修が一度きりであったり、業務の繁忙期に短時間で済ませたりすると、操作の背景にある目的や安全な取り扱いの勘所が伝わりません。
役割別のカリキュラムや、交代勤務を考慮した反復学習の仕組みがないと、わからない点を現場で相談しづらく、独自の回避手順が増えて混乱します。さらに、更新時の変更点周知やマニュアルの見直しが追いつかないと、古い手順が残り、トラブル時の対応が属人化します。
小さな習熟度の差が積み重なるほど、現場は新機能の活用に消極的になり、医療DXが進まない循環が生まれます。
院内には電子カルテ、検査、画像、会計、勤怠、在庫など多数のシステムがあり、世代や提供元が混在しています。新しい仕組みを導入しても、データ形式や識別子の違いで情報が往復できないと、二重入力や紙出力の確認が残ります。連携の設計や検証の工数を見積もらないまま導入を急ぐと、現場の負担が増え、期待していた効果が思うように出ないことがあります。
従来の電子カルテや会計・レセプトシステムは、開発元独自の仕様で動いていることが多く、標準化が不十分な項目や固定長の出力に依存している場合があります。その為、クラウド型の予約・問診や地域連携のプラットフォームと連携させる際に、項目のマッピングが合わず、手作業で補正せざるを得ない場面が生じます。
結果として、導入直後は便利に見えても日々の運用で例外処理が増え、最終的には「前より手間がかかる」と受け止められてしまいます。互換性の溝を埋めるには、現状のデータ項目と新システムの項目設計を丁寧に突き合わせ、将来の拡張も見据えた移行計画が必要です。
患者基本情報、診療履歴、検査結果、画像リンク、帳票テンプレートなど、移行すべきデータは多岐にわたります。移行前の精査を怠ると重複や表記ゆれが温存され、新システムで検索性が落ちます。さらに、移行期間の運用二重化や停止時間の調整、バックアップとロールバック手順の準備など、見えにくい作業が連続します。
もし不整合や欠損が起きれば、診療の遅延や再検査の発生につながりかねません。安全に前に進むには、段階移行の計画、テスト用データの作成、検証用のチェックリスト整備など、地道な下準備が欠かせません。
医療DXは初期導入費だけでなく、保守、更新、教育、サイバー対策、回線や端末の更新といった継続費が伴います。限られた財源のなかで優先順位をつける際、短期の収益改善と比べて効果が見えにくいと投資判断が遅れます。
同時に、院内に運用を支える人材がいなければ、外部に依存し、問題解決のスピードが落ちます。特に小規模クリニックや地方では、この二つの壁が重なりやすいのが現実です。
人件費や機器保守、建物維持など固定費の比率が高いなかで、DXの関連費用は新規枠として確保する必要があります。電子カルテや予約・問診、セキュリティ強化、バックアップ環境整備まで含めると、初年度の支出は高額になる可能性があります。費用対効果の算定が曖昧なままだと意思決定の妨げになります。
導入後の時間短縮やミス削減、回収率の改善などを指標化し、段階導入で負担を平準化する枠組みを持たないと、日々の運転資金に押されて投資が後回しになります。結果的に、老朽化した環境の維持費がかさみ、負の循環に陥ります。
院内にシステム運用と改善を担う人材がいない場合、設定変更やトラブル対応のたびに外部に依頼することになり、対応の遅れとコスト増が発生します。
一方で、医療領域に明るく、現場導線を理解したIT人材は市場でも不足しており、採用競争が厳しい状況です。既存スタッフに期待しても、通常業務が逼迫して学習時間を捻出しにくく、担当者の属人化を招きます。
役割定義、育成計画、外部パートナーの活用を効率的に組み合わせることで、スムーズに改善させることができます。
医療は安全と正確さを重視するため、手順の変更や新ツールの導入には慎重になりがちです。目的や効果が現場に伝わらないまま進めると、「今のやり方でも支障はない」という空気が強まり、試験導入後に元に戻る現象が起きます。
改善の理由と期待される成果、リスク低減の方法を共有し、現場の不安に向き合う姿勢が欠けると、DXは定着しません。
使い慣れた業務フローは安心感を与える一方、新しい画面や操作は負担として受け止められます。導入期に細かな不具合や操作遅延が続くと、印象が悪化し、学習や提案の意欲が下がります。また、評価制度や勤怠の仕組みが改善活動を後押ししないと、現場は追加作業にしか見えません。
抵抗感を和らげるには、小さな成功体験を積み上げ、改善が自分たちの仕事を楽にする事実を可視化することが重要です。疑問点を気軽に出せる場や、改善提案が認められる雰囲気づくりも欠かせません。
紙の帳票、口頭での連絡、手作業の集計など、長年続いたやり方は「当たり前」として根付いています。フローの見直しを伴わずにシステムだけを入れると、旧来の手順が温存され、二重の手間が残ります。
まずは目的と成果物を再設計し、不要な承認や重複入力を削ることが先決です。そのうえで、画面や帳票を現場の動線に合わせて整えると、負担が減り定着が進みます。固定化を解くには、トップの方針と現場の声の両輪で、段階的にルールを更新していく姿勢が求められます。
医療DXが進まない状況では、負担の偏りや手戻りが慢性化し、診療の質・スピード・安全性に波紋が広がります。
紙の帳票や口頭確認が残るほど業務は複雑になり、データの重複入力や確認作業が増えて現場の疲弊を招きます。さらに、セキュリティ体制の甘さや患者とのコミュニケーション変化に十分対応できなければ、トラブル時の影響は一気に拡大します。
ここでは、現場が抱える悩みを「運用のギャップ」「情報セキュリティ」「患者対応」の観点から整理し、なぜ医療DXが進まないのかを具体的に捉えます。
医療DXの必要性は共有されていても、導入・運用・教育の設計が不足すると、現場は「便利になるはずが手間が増えた」と感じます。試験導入の範囲が狭く、既存フローの見直しを伴わないままシステムだけが増えると、二重管理や例外処理が膨らみます。
結果として、医療DXが進まない印象が強まり、改善の好循環が立ち上がりません。
紙の問診票、手書きの指示、電話中心の連絡などが残ると、入力・転記・確認の工程が分散し、担当者ごとに解釈がぶれやすくなります。部門ごとに表計算で患者情報を個別管理する運用は、最新版の所在が曖昧になり、探す・照合する・修正するといった作業が積み上がります。
電子カルテや予約システムを導入しても、紙の運用を並行させると二重入力が続き、残業や待ち時間の増加へ直結します。加えて、口頭確認に依存した運用は引き継ぎの漏れを生みやすく、インシデントの芽を早期に潰せません。
こうした非効率が積み重なることで、現場は「変えるほど忙しくなる」と感じ、医療DXの導入が滞る原因となります。
現場は「入力の簡素化」「確認の自動化」「情報の一元化」に期待しますが、導入対象を局所に限定すると全体の流れは改善されません。例えば、オンライン予約だけ更新しても、問診や会計が従来のままなら、窓口での再入力や照合作業が発生します。
運用手順や役割分担の見直しを伴わずに機能だけ追加すると、例外時の逃げ道が増え、誰がいつ何を確認するかが不明瞭になります。教育やマニュアルが一次対応の現場に届いていないと、問い合わせが集中し、改善提案も上がりにくくなります。期待した効果が出ない状態が続くほど、「医療DXが進まない」という評価が定着し、投資判断も慎重になってしまいます。
電子カルテ、画像、検査、会計、地域連携までデータの流通が広がるほど、アクセス管理と記録の厳密さが求められます。ところが、複数システムの組み合わせや端末の持ち出し、クラウドの活用が進むと、責任分界や更新手順が曖昧になりがちです。現場の運用に沿ったルールと監査の仕組みが整わない限り、医療DXは安心して前に進みません。
閲覧権限の粒度が粗い、共有アカウントが残っている、退職・異動時の権限剥奪が遅れるといった問題は、小さな見落としから重大な漏えいへ発展します。
端末の自動ロックや持ち出し制限、画面覗き見対策、ログの定期確認など、基本的な仕組みが徹底されていない施設もあります。中小規模では専任担当が不在なことが多く、システム更新や脆弱性対応が後回しになりがちです。
結果として、現場はリスクを恐れて新機能の利用を控え、医療DXの活用範囲が狭まります。まずは権限設計と台帳管理、端末・媒体の統制を明確にし、日々の点検を定例化する土台づくりが欠かせません。
多層防御を整えるには、エンドポイント対策、メールフィルタ、脆弱性管理、バックアップ、侵入検知、暗号化、ログ監査、職員教育など幅広い投資が必要です。単発のライセンス購入だけでは十分ではなく、更新・検証・訓練に継続費が発生します。
費用見通しが曖昧だと導入は遅れ、暫定運用が長期化してリスクが高まります。現場目線では、操作負荷の増加や誤検知による業務停滞も懸念材料です。効果と負担のバランスを可視化し、段階導入や重要資産からの優先整備、演習の定例化で実効性を高める設計が求められます。
こうした体制が整ってはじめて、医療DXは安心して拡張できます。
オンライン予約・問診、キャッシュレス、ポータル配信などが広がると、来院前後の接点がデジタルへ移行します。利便性は高まる一方で、操作に不慣れな層には負担となり、窓口の案内や電話対応がかえって増える場合もあります。
診療中は画面操作が増えやすく、説明やアイコンタクトが減ると不安や不満が蓄積します。移行期の支援設計が不足すると、「医療DXが進まないほうが安心」という声が現場に残ります。
高齢者やスマートフォンに不慣れな方にとって、アプリのインストール、ログイン、予約変更、事前問診の入力は心理的な壁になります。入力ミスや通信不良が起これば来院時に再入力が必要となり、待ち時間や負担感が増します。
紙の診察券や対面説明の安心感を重視する患者にとっては、通知やチャットだけでは理解が追いつかないこともあります。こうした戸惑いは現場の追加支援を生み、導入効果を実感しにくくなります。
段階的に選択肢を用意し、窓口での丁寧な案内や代替手段を並走させることで、移行期のストレスを最小化できます。
受付・会計が速くなっても、診療時の対話が減れば満足度は伸び悩みます。画面入力に時間を要すると、説明や共感の時間が圧縮され、理解不足や不信感につながります。また、システム障害や操作に迷いが発生した際のリカバリー手順が定まっていなければ、待合の混雑や問い合わせの増加を招き、患者の満足度が低下します。
逆に、説明資料のテンプレート化や事前配信、記録の要点整理を活用すれば、対話の質を保ちつつ効率化が図れます。現場は「省力化」と「伝わる説明」の両立を意識し、患者が安心できる導線を設計することが大切です。

医療DXが進まない背景には、技術・人材・運用・文化のそれぞれに根差した要因が複合しています。逆にいえば、施策をばらばらに導入するのではなく、教育とサポート、連携の設計、費用と体制の最適化、現場の意識づくりを同時並行で整えることで、停滞は解けます。
ここでは、各医療機関の規模や機能に合わせて無理なく着手できる現実的な手立てをまとめ、負担を増やさず成果を積み上げる運び方を示します。小さな成功を確実に積み重ね、混乱を避けながら範囲を広げることが、医療DXの定着を早める近道です。
ITに不慣れな職員が一定数いる状況でも、役割別に学ぶ内容と支援の受け皿を整えれば、日常運用は安定します。目的は高度な技術習得ではなく、「安全に迷わず使えること」と「困ったらすぐ頼れる体制」を両立させることです。
教育を一度で終わらせず、勤務形態に合わせて反復できる仕組みにすると、現場の抵抗感が薄れ、改善提案も出やすくなります。
研修は職種別・熟練度別に分け、短時間の反復で定着を促す設計が効果的です。受付・会計・看護・医師などの導線に合わせ、電子カルテの入力テンプレート、予約変更、検査内容、説明資料の印刷や共有といった必須操作を実践形式で扱います。
集合研修とeラーニングを組み合わせ、動画・チェックリスト・よくある質問を配布します。交代勤務に合わせて複数枠を設け、ロールプレイで患者対応を想定した操作手順を確認します。到達度は小テストや実地観察で可視化し、間違えやすい操作は画面のショートカットや凡例を整備します。
更新時は変更点だけ学べる補講を設け、負担を抑えながら最新の運用にそろえます。
日々の疑問や不具合をすぐ解消できる窓口があると、現場は安心して使い続けられます。院内の問い合わせ窓口を一本化し、連絡先と対応時間、一次対応と二次対応の分担を明確にします。
よくある質問は院内ポータルに集約し、画面付きの手順書と短い動画を用意します。端末・周辺機器・アカウントの台帳を整え、入退職や異動に伴う権限更新を定例化します。障害時は代替運用の手順(紙での受付や後追い入力の流れ)を整備し、年に数回の訓練で手順を確認します。
ベンダーとの連絡経路や対応水準も文書化し、復旧の目安と連絡の頻度をあらかじめ共有しておくと、現場の混乱を防げます。
連携の成否は、技術選定よりも「どのデータをどの場面で誰が使うか」を先に定義できるかで決まります。まず現状の入力・確認・出力の流れを図にし、重複や滞留を特定します。その上で、優先度の高い接点から段階的に刷新し、試験運用で例外処理を洗い出してから範囲を広げると、安全に定着します。
一気に刷新すると現場負担が跳ね上がるため、予約・問診・会計など患者の体験に直結し効果が見えやすい領域から始めます。先行導入の部署を決め、小規模な試行で画面と帳票の体裁、データ項目の対応表、手戻り時の代替手順を整えます。
並走期間を設け、紙とデジタルの差異を記録しながらルールを一本化します。移行は停止時間を短く分割し、事前のデータ整理とバックアップ、ロールバック手順を用意します。
導入後は入力時間、待ち時間、問い合わせ件数などの指標を週次で確認し、設定の微調整を繰り返して現場の負担を減らします。これにより、混乱を抑えつつ次の領域へ拡張できます。
クラウドは初期費用の平準化や更新の容易さにメリットがありますが、守りの設計を同時に進めてこそ効果が生じます。通信の暗号化、多要素認証、役割に応じた細かな権限、操作記録の保全を基本に、定期点検と改修の流れを定例化します。
重要データは世代管理したバックアップを異なる場所に保持し、復旧手順を訓練で確認します。端末の持ち出し制御、画面の覗き見対策、メディアの管理、退職・異動時の権限停止など運用の基本も徹底します。
外部サービスを採用する場合は、可用性やデータ保管場所、障害発生時の通知と対応水準を文書で確認し、院内の責任分担を明確にしておくと安心です。
限られた資源で前に進むには、投資の優先順位づけと、外部の力の取り込み、そして業務効率化による原資づくりが有効です。費用対効果を数値で示し、小さな改善から確実に効果を出すと、次の投資への理解も得られます。人材面は、院内育成と外部協力の組み合わせで継続可能な体制に整えます。
不足しがちな専門性は、外部の力を計画的に借りることで補えます。要望と現場の制約を整理した要件書を作成し、導入・移行・運用の役割分担と対応水準、費用の内訳を明確にします。
段階導入ごとに成果物と検収基準を決め、障害時の連絡体制と復旧目安を合意します。長期的には、特定の業者に依存しすぎないよう、データの書き出し形式や接続仕様を事前に確認し、将来の拡張に備えます。
定例会議で現場の困りごとを共有し、設定の見直しや画面改善を継続することで、導入後の使い勝手が着実に向上します。
費用を捻出する最短の道は、日常の無駄を減らして原資を生み出すことです。予約・問診の事前入力、受付の自動呼び出し、会計の自動計算、書類の電子保管を進めると、転記や照合の時間が減ります。診療情報のテンプレート化や定型文の活用、検査予約の調整ルール化、問い合わせの定型回答準備も有効です。
効果は「待ち時間」「再来率」「残業時間」「問い合わせ件数」などの指標で確認し、浮いた時間を患者説明や安全確認に振り向けます。こうして生まれた余力を次の更新や教育の費用に充てると、改善の循環がまわり始めます。
仕組みだけでは定着せず、日々の行動を変える後押しが必要です。方針は院内で共有し、目的・期待する効果・役割分担・評価の観点を明確にします。小さな改善でも正当に評価し、現場の提案が取り上げられる環境をつくると、前向きな動きが広がります。
トップの後押しと現場の創意工夫がかみ合うほど、組織としての質がどんどん上がるでしょう。
部署横断の小さなチームをつくり、受付から会計までの動線を一枚の図にして課題を可視化します。改善は短い期間で区切り、達成したい指標と評価日を決めます。週次の打ち合わせで困りごとを洗い出し、設定変更や帳票修正を素早く反映します。また、患者の声を定期的に集め、導線の詰まりや説明不足を検証します。担当者が固定化しないよう役割を交代し、属人化を防ぐことも大切です。
こうした地道な運営が、現場に合ったDXの姿を形づくり、持続的な改善につながります。
効果が見えた取り組みは、数字と具体例で院内に共有します。待ち時間の短縮や問い合わせ減少、入力の簡素化などを図表で示し、誰の負担がどれだけ軽くなったかを明らかにします。
改善に関わった職員の工夫や学びを紹介し、次の挑戦を後押しします。失敗例も教訓として共有し、責めるのではなく再発防止の手順に落とし込みます。成功と学びを循環させることで、現場は「変えるほど楽になる」という実感を得られる為、医療DXへ前向きに取り組むようになります。

「医療DXが進まない」と感じる現場でも、着眼点と運び方を少し変えるだけで前進は可能です。本セクションでは、無理のない段階導入で成果を出した事例、費用面の壁を低くする補助金や支援の活かし方、そして継続して改善を回す体制づくりの考え方をまとめます。
規模や診療科により事情は異なりますが、共通するのは「できるところから始め、効果を見える化し、次の一歩につなぐ」という進め方です。現場の悩みに寄り添った実践例と支援策の要点を手掛かりに、自院に合ったロードマップを描いていきましょう。
成功している医療機関は、一度に大掛かりな刷新を狙うのではなく、予約・問診・会計など効果が見えやすい領域から着手し、指標で成果を確認しながら範囲を広げています。
現場の声を画面や帳票の設計に反映し、短いサイクルで改善するのが特長です。結果が共有されるほど職員の不安は薄れ、次の導入が進みやすくなります。
ある中小病院では、まず外来の予約と事前問診をオンライン化し、受付の混雑を抑えることから始めました。導入前に動線と帳票を見直し、紙とデジタルの二重運用を最短で終える計画を明文化しました。
現場代表を交えた試行期間を設け、画面の文言やボタン配置を修正しながら定着させました。次に、検査オーダと会計の連携を段階的に拡張し、診療データの抜けや転記を減らす運用へ移行しました。週次で「待ち時間」「問い合わせ件数」「後追い入力時間」を計測し、改善点を可視化して共有しました。
教育は職種別に小分けし、更新時は変更点だけ学べる補講で負担を軽減することができました。こうした積み重ねにより、残業削減と再鑑確認の時間確保を両立し、患者説明の質も向上しました。
小規模クリニックでは、オンライン予約・事前問診・キャッシュレス会計を組み合わせ、窓口の電話応対と紙管理を大幅に削減しました。来院前に患者情報がそろうため、診察中の入力はテンプレートで要点を押さえ、説明資料を自動出力できるようにしました。受付では自動呼び出しを採用し、待合の滞留を抑制しました。
導入後は「受付から会計までの平均所要時間」「問合せの再連絡率」「入力の差戻し件数」を月次で確認し、画面や文言を微調整。操作に不安のある患者には紙の代替手段を並走させ、移行期のストレスを軽減しました。
結果として、事務の残業が減り、医師・スタッフの対話時間が確保され、患者満足度の改善につながりました。
費用の壁が高いと感じる場合でも、国や自治体の支援を組み合わせれば導入ハードルは下がります。対象となるシステムや要件、申請の流れは制度ごとに異なるため、最新情報の収集と書類準備の段取りが重要です。院内の体制づくりと並行して計画的に申請すると、予算確保の見通しが立ちやすくなります。
代表例として、IT導入を後押しする補助制度や、医療分野のデジタル化・セキュリティ強化を対象とする助成があります。電子カルテや予約・問診、情報共有、バックアップ環境、セキュリティ対策など、院内の優先度に応じて幅広く活用が可能です。自治体独自の上乗せや、地域医療の連携基盤を対象にした支援が設けられる場合もあるため、医師会や商工団体、自治体の窓口から最新情報を入手すると良いでしょう。
採択後の実績報告や保守運用の要件まで見据えて計画に織り込み、導入後の費用と体制を継続可能な水準に整えることが、現場の負担を増やさないコツです。
まず、現状の課題と改善目標を簡潔に整理し、対象システム・導入範囲・スケジュール・効果指標(待ち時間、問い合わせ件数、残業時間など)を計画書に落とし込みます。
見積は機能別に分け、初期費・保守費・教育費・データ移行などの内訳を明確化しましょう。要件に合致するかを事前に確認し、不足があれば範囲や構成を調整します。申請後は、進捗の記録や導入実績のエビデンス(スクリーンショット、研修記録、運用マニュアル)を整理しておくと、報告がスムーズです。
手続きが複雑な場合は、ITベンダーや専門家へ早めに相談し、申請・納品・報告の役割分担を文書で取り決めると、行き違いを防げます。
単発の導入で終わらせず、継続して改善を回す仕組みづくりが重要です。目的・役割・評価の物差しを共有し、短い周期で見直すと現場の納得感が高まります。ベンダーとの協働を定例化し、障害対応や小規模な画面改修を迅速に回せると、定着が加速します。
現場の導線や制約を理解したうえで、要件を「誰が・いつ・どの画面で・どのデータを確認するか」に落とし込み、試行の段階で画面・帳票・通知の体裁を調整します。連絡経路と対応水準(初動の目安、報告頻度、代替運用)を合意し、障害時の手順を共有しましょう。
定例会では、数値指標と問い合わせ内容を振り返り、設定変更やテンプレートの改善を継続します。将来の変更に備えて、データの書き出し形式や接続仕様の確認、権限設計とログの取り扱いを文書化しておくと、拡張や乗り換えもスムーズです。
院内に小さな推進チームを置き、受付から会計までの流れを可視化して課題を定例で見直します。週次・月次で「待ち時間」「入力時間」「問い合わせ件数」などを追い、改善の優先度を決定しましょう。教育はローテーションや代替要員を考慮し、更新時は変更点だけの短時間研修で負担を抑えます。
評価は成果と学びの両方を対象にし、成功例は図や手順で共有、失敗例は再発防止の手順に反映します。こうした仕組みが回り始めると、医療DXが進まない原因は段々と解け、現場の安全と患者体験の向上が同時に実現します。
医療DXが進まない理由には、ITリテラシー不足、既存システム連携の難しさ、予算や人材の不足、現場の意識改革の遅れなど多岐にわたる課題があります。
しかし、現場向けIT研修やサポート体制の強化、段階的なシステム更新、外部ベンダーの活用、補助金制度の積極的な利用、そして現場の意識改革・リーダーシップの発揮により、これらの進まない理由を一つひとつ克服することが可能です。
医療DX導入の成功事例と支援策を参考に、自院や現場に合った計画的なDX推進を進め、より質の高い医療サービスと効率的な運営を実現しましょう。
今後も持続的なDX推進体制の構築と現場全体での意識共有が、医療DXを推進させるカギとなります。

お気軽にご相談ください
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 柴田雄一
株式会社ニューハンプシャーMC
代表取締役
米国MBA留学後大手経営コンサルティング会社を経て2004年当時では珍しかった医業経営コンサルティングに特化したニューハンプシャーMCを設立。20年以上にわたる深い知見とユニークな視点からの具体的な支援がクライアントからの高い信頼を獲得し続けている。またそのユニークな視点を言語化した医業のマーケティング、スタートアップ(開業)、マネジメントをテーマにしたプロフェッショナルシリーズをそれぞれ出版し、影虎(本の登場人物の経営コンサルタント)ファンも数多い。
南ニューハンプシャー大学経営大学院(MBA)卒