「患者数が伸びず、広告費だけが膨らむ...」
そんな悩みを抱えていませんか?
人口減少や競合クリニックの増加で、ただ待つだけでは患者は集まりにくい時代です。
この記事では、病院・クリニックが限られた予算で効果的に集患し、地域で選ばれる存在になるためのマーケティング戦略を解説します。
具体的な内容としては、市場分析のやり方からオンライン施策、オフライン施策、スタッフ教育、さらにKPIで成果を可視化して改善を重ねる方法まで、初めてマーケティングに取り組む医療機関でも再現できる具体策を解説していきます。
ぜひ自院の状況と照らし合わせ、最適な打ち手を選択してください。
目次
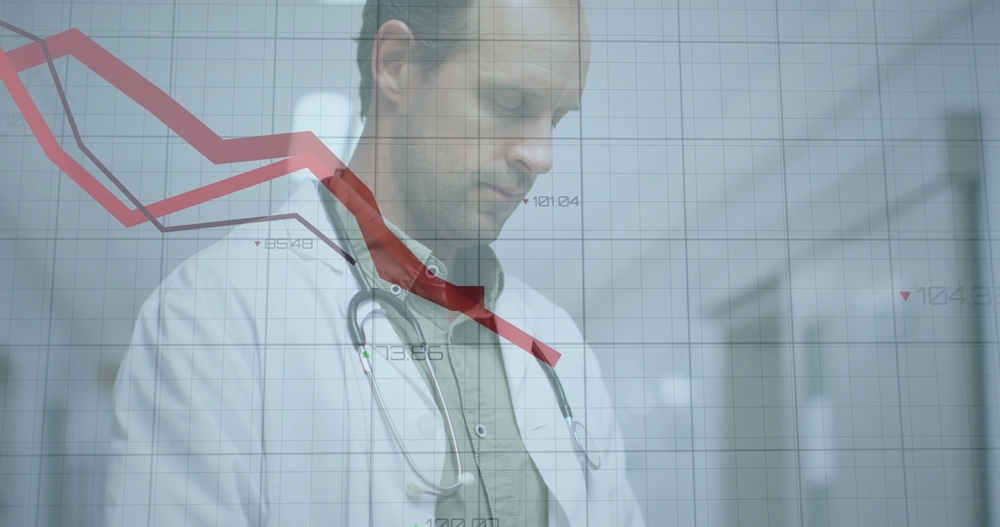 診療報酬の抑制や少子高齢化で外来患者数が頭打ちになる一方、開業クリニックは増え続けています。待っていれば患者が来院する時代は終わり、医療機関も地域で選ばれるための情報発信と価値訴求が欠かせません。
診療報酬の抑制や少子高齢化で外来患者数が頭打ちになる一方、開業クリニックは増え続けています。待っていれば患者が来院する時代は終わり、医療機関も地域で選ばれるための情報発信と価値訴求が欠かせません。
ここでは、病院がマーケティングを導入すべき理由を順番に解説していきます。
人口構造の変化により高齢患者は増えているものの、若年層は減少し、診療科によっては患者総数が右肩下がりです。
さらに2021年のオンライン診療解禁や2024年のリフィル処方箋拡大など制度改正が相次ぎ、患者の受療行動は「通いやすさ」から「便利さ」へシフトしました。
競合は同業の病院だけでなく、在宅医療や遠隔医療サービスにも広がっています。こうした外部環境を正しく把握し、自院の立ち位置を再定義することがマーケティングの第一歩です。
患者は症状だけでなく診療時間・待ち時間・プライバシー配慮・スタッフ対応など総合的な体験価値で医療機関を選択します。口コミサイトやSNSで情報収集が容易になり、小さな不満でも瞬時に共有されるため、良質な体験を提供できなければ新患獲得もリピーター確保も困難です。
競争激化の中で生き残るには「誰に」「何を」「どのように」届けるかを戦略的に設計し、継続的に改善する流れが不可欠です。
マーケティングは広告施策にとどまらず、強みの分析からターゲット設定、差別化コンセプト創出まで一連のフローで考えることで最大効果を発揮します。
各ポイントを順に掘り下げ、実務で活用できる手順と注意点を解説していきます。
まずは診療圏調査ツールや統計資料で商圏人口・年齢構成・競合施設数を把握し、自院のポジションを定量的に可視化します。
競合サイトやチラシを確認すると、診療科目や特徴が似通うケースも多いです。診療時間・専門医有無・医療機器など差別化可能な項目を洗い出し、SWOT分析で「選ばれる理由」を抽出しましょう。
強みが明確になれば、施策の優先順位が決まり、広告費の無駄打ちを防げます。
想定患者像を年齢・性別・生活圏・ライフスタイル・悩み別にペルソナ化し、来院前後の行動フローを描きます。
例として30代子育て世帯は小児科と内科を併用する傾向があり、夜間・休日診療の需要が高めです。
こうした洞察を基に「どの患者層にリソースを集中すべきか」を定めると、メッセージや媒体選定が一貫します。
強みとターゲットの交点から「地域初のスポーツ整形」「女性医師による婦人科外来」のような分かりやすい価値提案をまとめます。コンセプトは院内掲示・ウェブサイト・求人情報まで統一し、スタッフ全員が共有することで接遇品質もそろいます。
差別化が伝われば、価格競争に巻き込まれず適正な診療単価を維持できます。
 スマホ検索やSNSで医療機関を探す患者が主流となり、オンライン施策は集患の中核になりました。検索エンジン、地図アプリ、公式サイト、SNSを連携させて来院までの導線を可視化すると、広告費を抑えながら新患を継続的に獲得できます。
スマホ検索やSNSで医療機関を探す患者が主流となり、オンライン施策は集患の中核になりました。検索エンジン、地図アプリ、公式サイト、SNSを連携させて来院までの導線を可視化すると、広告費を抑えながら新患を継続的に獲得できます。
次からは各施策を順に深掘りし、実務に落とし込むための手順と注意点を解説します。
SEOは24時間患者と接点を持てる低コスト施策です。医療広告ガイドラインを順守しつつ検索意図を捉えた記事を量産すれば、指名検索や地名×診療科キーワードで上位表示を狙えます。サイト構造を最適化し、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の証拠を盛り込むことで検索エンジンと読者の双方から評価されやすくなります。
狙うキーワードは「地名+診療科+症状」で月間検索ボリューム100〜500のミドルレンジを中心に選定します。検索意図を「受診判断」「治療方法」「費用相場」などに分類し、タイトルにはキーワードを30字以内で自然に含めます。医療法で限定される表現を避けつつ、患者がクリックしたくなる具体性のある言葉を配置することが重要です。
トップページから診療科、症状解説、治療法の詳細へ3クリック以内で到達できる階層構造にします。関連ページ同士を内部リンクで結ぶと、クローラーが巡回しやすくなりページ評価が全体に分散します。パンくずリストを実装し、MDファイルで構造化データを設定するとリッチリザルト表示も期待できます。
過度な効果保証やビフォーアフター画像はガイドライン違反となるため、施術効果は学会ガイドや論文を根拠に定量的に示します。専門医資格や学会発表歴を明示し、第三者機関の認定マークを掲載すると信頼性が高まります。ガイドラインチェックリストを運用し、記事公開前に表現を精査する体制を整えましょう。
GBP(Google Business Profile)は地図の検索結果に表示される無料の集患チャネルです。カテゴリや診療時間を正確に登録し、写真・投稿機能で院内設備や季節情報を発信するとクリック率が上がります。口コミ返信を継続するとエンゲージメントが高まり、ローカルパックで優先表示される確率が向上します。
主カテゴリには「内科医院」など診療科を選定し、副カテゴリで専門外来を補足します。診療時間は祝日や臨時休診も含め正確に設定し、患者が行動する前に情報の齟齬を防ぎます。予約リンクやメニュー機能を使い、公式サイトへシームレスに誘導すると離脱を減らせます。
外観、受付、診察室など計6枚以上の解像度の高い写真を掲載すると閲覧数が平均3倍に伸びるというデータがあります。
季節の装飾やキャンペーン投稿を毎週更新し、最新情報を届けると再訪率が向上します。画像のファイル名にキーワードを含めると画像検索流入も期待できます。
口コミは評価スコア以上に「返信率」で信頼度が測られます。★3以下の投稿にも感謝と改善策を明確に伝え、ポジティブ口コミには丁寧に謝意を示します。平均返信時間を48時間以内に抑えるとエンゲージメントが高まり、アルゴリズム上も優遇されやすくなります。
サイトでは医師紹介、診療内容、料金表など一次情報を網羅し、ブログで症状別セルフケアや季節の健康情報を毎月2〜3本更新します。
記事の最後にWEB予約ボタンやLINE友だち追加リンクを設置すると、読了後の行動を促進できます。オウンドメディアを育てることで広告費を抑えつつ中長期で流入が伸び続けます。
ターゲット層に合わせてInstagramやX(旧Twitter)を選定し、診療の裏側や医師の人柄が伝わる投稿を週2回発信します。
ストーリーズで当日予約枠を告知するとキャンセル埋めにも有効です。ハッシュタグに地名+診療科を入れ、インフルエンサーとのコラボでリーチを拡大すると地域認知が一気に広がります。
デジタル施策だけではリーチできない高齢層や医療機関同士の紹介を獲得するには、地域密着型のオフライン施策が不可欠です。顔の見える関係性を築くことで口コミが広がり、広告に頼らない安定集患が実現します。
以下では来院ハードルを下げ、患者満足度を高める具体策を紹介します。
近隣診療所や介護施設、訪問看護ステーションと定期的に情報交換会を開催し、症例共有や逆紹介の窓口を明確化します。紹介患者の診療結果を当日中にレポート返送すると信頼が深まり、紹介件数が増加します。連携先一覧を院内掲示するとスタッフ全員が迅速に紹介ルートを案内でき、患者の不安も軽減されます。
生活習慣病予防や産後ケアなど地域課題にマッチした講座を毎月開催し、参加者に無料健康チェックや個別相談を提供します。イベントは自治体広報や商店街ポスターで告知し、参加者アンケートでメール配信の許可を得ると、後日のリマインドで受診につながります。講師を務める医師の専門性が伝わり、医療不信を払拭できる点もメリットです。
受付スタッフの笑顔・声掛け・待合室の衛生管理といった基本動作こそ口コミの源泉です。待ち時間を15分刻みで掲示し、遅延が見込まれる際はLINE呼び出し機能で外出を許可するとストレスが大幅に軽減されます。受診後にQRコードで簡単に口コミ投稿できるカードを配布し、投稿者には健康冊子を進呈するとポジティブ口コミが自然に増えます。
施策を実行しただけでは効果は見えません。重要なのは、数値で成果を把握し改善を重ねるサイクルを組み込むことです。来院数だけでなく質的指標も追うことで、患者満足度と経営効率を同時に高められます。
以下で、測定指標の選び方から改善手順まで具体策を示します。
最初に設定すべきKPIは「新患数」「再来率」「1人当たり診療単価」の3指標です。毎月の推移をスプレッドシートで可視化し、施策実施日の注釈を入れると因果関係が読み取りやすくなります。GA4やGBPインサイトからクリック数やルート検索数も取得し、オンライン施策との相関を分析すると改善の優先順位が明確になります。
定量指標だけでは患者体験の質は測れません。診察後に5問程度の患者満足度アンケートをタブレットで実施し、自由記述欄を設けると具体的な改善ヒントが得られます。結果は診療科別・時間帯別にクロス集計し、スタッフミーティングで共有すると改善意識が浸透します。1年に1回は設問を見直し、時の流れに合わせることが重要です。
KPIとアンケート結果を基に改善案を3か月単位で実行し、効果を検証します。例として、土曜午後の診療開始した際に新患数の20%増加を確認できたら施策を導入し、効果が薄い施策は早期撤退します。PDCAを定期運用することで、限られた人員でも高いマーケティング効果を維持できます。
 戦略を絵に描いた餅にしないためには、明確な役割分担と組織マインドが欠かせません。院内チームと外部パートナーを適切に活用し、スタッフ全員がマーケティングを「自分ごと」として捉える文化を築きます。
戦略を絵に描いた餅にしないためには、明確な役割分担と組織マインドが欠かせません。院内チームと外部パートナーを適切に活用し、スタッフ全員がマーケティングを「自分ごと」として捉える文化を築きます。
次段落で具体的な体制構築の手順を紹介します。
院長が最終意思決定者となり、事務長をプロジェクトマネージャーに任命すると意思疎通がスムーズです。院内では医師が医療情報の監修、看護師が患者の導線改善、受付がSNS更新を担当し、広告代理店やSEO会社には専門知識が必要な領域を外注します。月次報告会を設定し、数値と次月アクションを共有すると、院内外の連携が強化されます。
スタッフがマーケティングを理解しないまま施策を実行すると、接遇やオペレーションで矛盾が生じます。年4回の勉強会で患者体験やデジタルマーケティングの基礎を学び、成功事例を共有すると意識が高まります。成果を出したスタッフを表彰するインセンティブ制度を導入すると、現場主体で改善が回りやすくなります。
病院マーケティングは「環境分析→戦略設計→オンライン・オフライン施策→成果測定→改善」という一連の流れを組織的に回すことが成功のポイントです。環境変化を捉え、強みとターゲットを明確にした上で差別化コンセプトを策定し、SEOやGBP、地域連携など複数チャネルを連動させると、限られた予算でも安定的に集患できます。
KPI管理とPDCAを継続し、スタッフ全員がマーケティングマインドを持つ組織体制を構築することで、長期的な地域貢献と経営安定を両立できます。
ニューハンプシャーMCでは、医療に特化したコンサルティングサービスを提供しております。
開業や継承、集患に悩んでいる方は、ニューハンプシャーMCにご相談ください。
オンラインでの無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
また、弊社の考え、ノウハウが凝縮された書籍も販売しております。
弊社にお問い合わせいただく9割以上の方が、本を通じて弊社の考えに共感しお問い合わせいただいております。
お気軽にご相談ください
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 柴田雄一
株式会社ニューハンプシャーMC
代表取締役
米国MBA留学後大手経営コンサルティング会社を経て2004年当時では珍しかった医業経営コンサルティングに特化したニューハンプシャーMCを設立。20年以上にわたる深い知見とユニークな視点からの具体的な支援がクライアントからの高い信頼を獲得し続けている。またそのユニークな視点を言語化した医業のマーケティング、スタートアップ(開業)、マネジメントをテーマにしたプロフェッショナルシリーズをそれぞれ出版し、影虎(本の登場人物の経営コンサルタント)ファンも数多い。
南ニューハンプシャー大学経営大学院(MBA)卒